ON-PAM委員会2024第1部 前半 おしゃべり会@委員会「海外フェスティバルおしゃべり会」レポート
2025.6.27
日時:2024年3月9日(土)15:50-16:50
会場:BUKATSUDO HALL、オンライン
スピーカー:
ホスト 寺田凜、松波春奈
ゲスト 加藤奈紬
ON-PAM委員会2024第1部 前半 おしゃべり会@委員会「海外フェスティバルおしゃべり会」
「海外フェスティバルおしゃべり会」は、2023年冬に、ON-PAM会員である松波春奈・寺田凜の会員提案企画として初めて実施され、今回は、その第2弾として開催。ホストは、前回同様に松波春奈・寺田凜が務め、ゲストに豊岡演劇祭プロデューサーである加藤奈紬を迎えた(オンライン)。タイトルにある通り本企画は、海外の舞台芸術フェスティバルについて、登壇者の参加体験を中心に語り合うもの。はじめに、松波・寺田がそれぞれ、参加した海外フェスティバルの概要について話し始めた。
松波は2023年の夏、アーツカウンシル東京のアートマネジメント人材等海外派遣プログラムでエディンバラ・フェスティバル(イギリス)を訪れた。キュレーションされた演目が上演されるエディンバラ・インターナショナル・フェスティバルと公募のエディンバラ・フェスティバル・フリンジなど多数のフェスティバルが8月に集中して開催される。松波は1週間ほど滞在し、1日に5~6つもの公演をはしごするような、観劇漬けの生活をしたと語る(会場数が徒歩圏内に300弱もあり、上演時間も1時間程度だったため、これだけの公演数を1日で鑑賞できたという)。また、派遣プログラムの一環として、クリエイティブ・スコットランドや、ブリティッシュカウンシルといった英国のアーツカウンシルおよび、フリンジ事務局とのミーティング等も設定されていたそうだ。

寺田も同じく2023年の夏に台湾の台北を訪れ、台北アーツフェスティバルの枠組みのなかで開催された人材育成事業、ADAM Gathering(アダムギャザリング)に参加。アダムとは、Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performanceの略称。アジア太平洋地域のアーティストが交流できる機会として、レジデンス期間を経て作品発表をする企画や意見交換会などを実施している。観劇がメインとなる松波の滞在とは異なり、寺田は舞台芸術関係者によるトークセッションに参加するなど、海外の関係者との交流機会を得ることが中心の滞在だったという。
ゲストの加藤も、ホストに続いて海外フェスティバルへの参加経験を話す。加藤は、大学3年のときにアヴィニョン演劇祭(フランス)を訪れたそうだ。当時京都で学生生活を過ごしていた加藤は、市内で開催していた国際舞台芸術祭・KYOTO EXPERIMENTで海外作品にふれる機会が多かったそう。それをきっかけに海外の舞台芸術に興味をもち、ゼミの先生に相談したところ、アヴィニョンの視察をおすすめされたそうだ。
「駅を降りると街に大量のチラシが貼られていた。上演が終わっても剝がされることなく、さらにそのうえに、これから上演されるチラシが重ねられていった。普段の街のようすが想像つかないほど賑やか。チラシ以外にもさまざまな宣伝スタイルがあって、馬に乗って街を歩くアーティストがいたり…旗を掲げた宣伝車が走っていたり…。劇場でないところもフェスティバルの活発な雰囲気が続いていて非常に衝撃をうけた」と加藤は語る。また、他の海外経験として、ダブリン・ダンス・フェスティバル(アイルランド)や、2023年6~7月に開催されたテアター・デア・ヴェルト(ドイツ)への視察、タイで開催されたAPPキャンプ(1)を挙げた。
3名とも、各自が参加した海外フェスティバルの概要説明を終え、松波がトークテーマを投げかける。まずは「渡航前はどんな準備をしたか/するか」について。ゲストの加藤は、SNS等インターネットの情報収集を活用して、現地の様子やフェスティバル情報などを、しっかりと調べてから渡航するそう。寺田も加藤と同様に、ネットで下調べをするそうで、特に現地の歴史や社会情勢などを丁寧にリサーチすると答えた。松波も、制作を務めたカンパニーの公演で韓国に渡った際の経験を挙げながら、現地の歴史をリサーチすると語った。
松波は「歴史をリサーチすることで、海外から見た日本の捉えられ方について再認識することができる。全てを把握することはできないけれども、知っておくことで作品への理解が深まるのではないか。また、カンパニーメンバーで共有してみる時間を設けることも良いと思う」と語り、加藤・寺田も大きく頷いた。
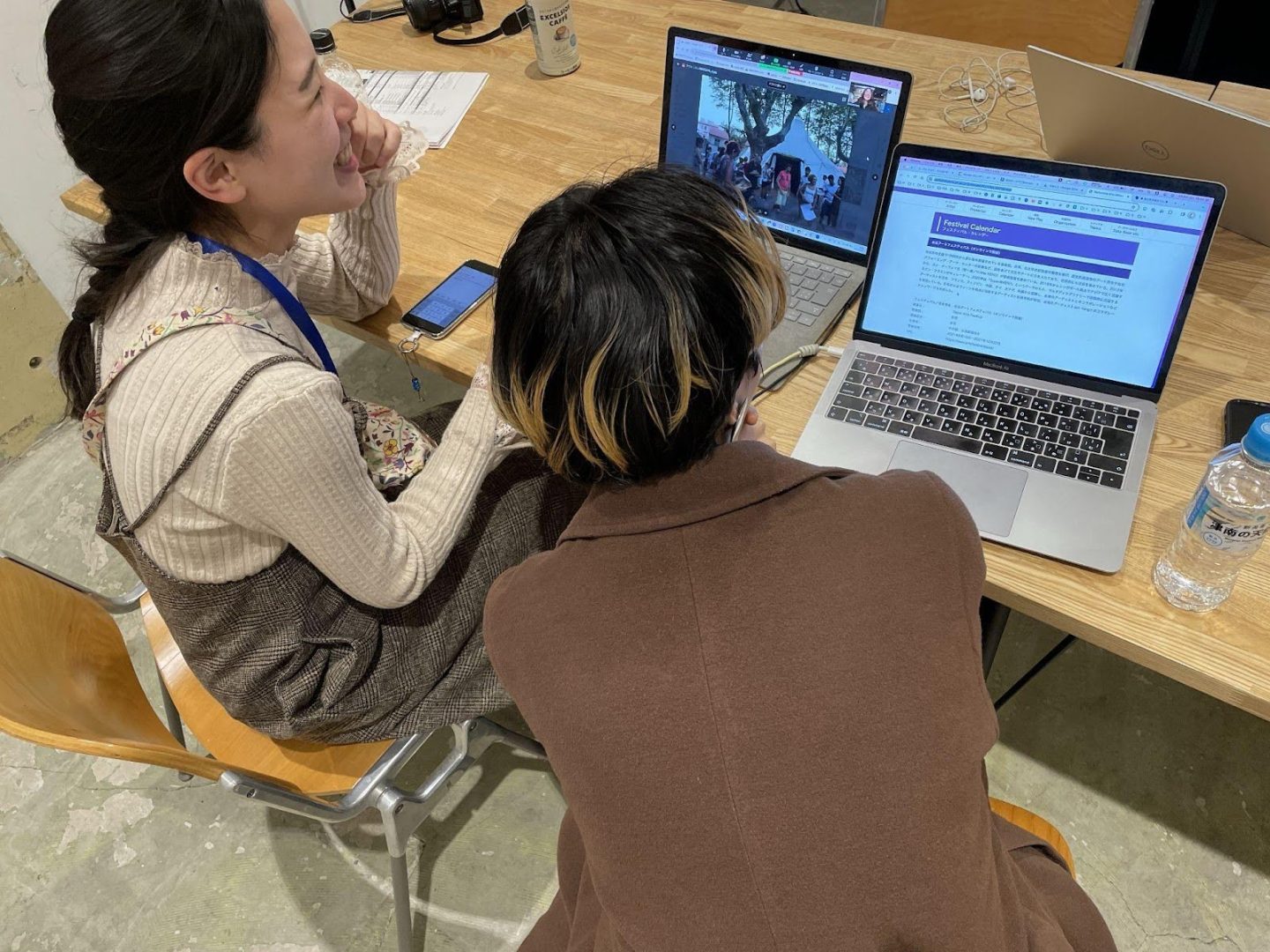
つづいて松波が、海外滞在中のちょっとしたエピソードがあれば共有できたらと声をかける。松波は、日本と異なり8月でも寒いエディンバラの気候に苦労したそう。寺田は、食事についてのエピソードとして、台北は都市部のためコンビニエンスストアが充実しており工面しやすかったと語った。加藤は、テアター・デア・ヴェルト(ドイツ)滞在前の体験を挙げる。渡航前に、本フェスティバル・ディレクターである相馬千秋氏が、日本から訪れる人へ向けた注意ガイドを、SNSで非常に丁寧に案内してくれていたそうだ。さらに、実際に渡航予定と分かっている人に対しては、メーリングリストにて出し惜しみなく、より具体的な案内を配信されていたそうで、貴重な情報ばかりで非常に助かったと語った。
終盤になり、参加者からも声があがる。
「フェスティバルに行くとたくさんの演目があって選ぶのが難しい」という悩みに対し松波は、それに共感しながら、エディンバラ・フェスティバルの際は口コミでおすすめのプログラム情報が届いてきたと語った。加藤は、自身がプロデューサーを務める豊岡演劇祭を例に挙げ「事前計画を立てずに、インフォメーションセンターで鑑賞プランを相談しにくる人がいた。演劇祭側も面白がってさまざまな場所を案内した。それもフェスティバルの良さだと思う」と語った。つづけて「アヴィニョンを訪ねた際は、外国語での会話に不安がありできなかったが、言語のハードルがなければ、現地の人に尋ねてみることも、とても良いと思う」と答えた。
次に他の参加者から「海外フェスの情報が一覧でまとまっているような場所はあるのか」という質問があがり、松波は、国際交流基金のWEBサイト(フェスティバル・カレンダー)を例に挙げた。(2025年6月27日現在閲覧できなくなっています。)さらに他の参加者から「おすすめの通訳アプリがあれば伺いたい」といった声もあがる。
寺田はGoogle翻訳や、DeepLを使用していたそう。加藤は、フランスを訪ねた当時は翻訳アプリの使用が一般的でなかったため、必要と思われる台詞を全て英語で紙に記して持ち歩いたと答えた。また、旅行で韓国を訪れた際には、Papagoというアプリを使用したと語った。アプリの話題はさらに盛り上がる。寺田は台北滞在時、英語の音声を書き起こしてくれるアプリ(Otter)も活用していたそう。「音声が英語でテキスト化されるので、会話のスピードが速く追いつけないときに、そのテキストを読んで補うようにした」という。
3人とも次回の海外フェスティバルを訪ねる計画は予定していないようだが、加藤は寺田の訪れた台北のADAMに関心を示していた。最後に松波が「皆さんの体験をお聞きできて嬉しかった。実用的なことも今後よりシェアしていきたい」と語り、海外フェスティバルおしゃべり会の定期的な開催を望みながら、この会を締め括った。
(1)…アジア大洋州地域の舞台芸術プロデューサー・制作者のプラットフォーム形成を目的としたインディペンデントな繋がりとして2014年に始まったAsia Producres Platform(APP)が行う、毎年アジアの国・地域に集まり、開催地域のリサーチをしながらネットワーキングを行う7日間のキャンプ事業。
執筆:臼田菜南